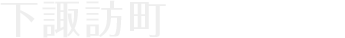後期高齢者医療制度について
最終更新日: 2025年10月1日
平成19年度に廃止された老人保健制度を引き継ぐ制度として、翌年の平成20年度より創設された医療保険制度です。
各県単位の制度であり、長野県内全市町村共通の制度で長野県後期高齢者医療広域連合が運営しています。
県内の市町村に住民登録をしていることにより対象者として判断します。
お手続きの窓口は住所地市町村単位となり、下諏訪町では住民環境課国保年金係が窓口となります。
対象者(被保険者)
(ア) 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から被保険者になります。)
(イ) 65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方(本人の申請に基づき、長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方。)
※認定の申請については国保年金係までご相談ください。
後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険やその他健康保険の被保険者及び被扶養者ではなくなります。
今まで加入していた保険との関係
・国民皆保険制度となりますので、全ての住民は国保、共済、その他健康保険組合等何らかの保険制度に加入しています。75歳以上の方が対象の後期高齢者医療制度は新しい保険制度です。
・75歳の誕生日前日まで加入していた健康保険制度から抜け、後期高齢者医療制度に加入していただくことになりますが、本人が後期高齢者医療制度へ移行する事に関しての申請は必要ありません。ただし、被扶養者の方については、別途国民健康保険加入のお手続きが必要となりますのでご注意ください。なお、同時に2つの保険に加入することは出来ません。
資格確認書等について
マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかることができます。マイナンバーカードを紛失した場合や、マイナ保険証での受診が困難である場合には、申請をいただくことで資格確認書を交付します。申請の際は、被保険者本人や家族、介助者による代理申請も可能です。資格確認書の発行を希望される際は国保年金係までお問い合わせください。
資格情報の更新
毎年8月1日を基準日として、一部負担金の割合を再判定いたします。マイナ保険証の登録の有無に関わらず、資格確認書を発行する期間を令和8年7月末まで延長しています。令和8年8月より、マイナ保険証をお持ちの方には【資格情報のお知らせ】を、マイナ保険証をお持ちでない方には【資格確認書】を郵送します。
マイナ保険証の登録解除
マイナンバーカードの紛失等の理由により、マイナ保険証の利用登録解除の申請をすることができます。申請の際は、被保険者本人や家族、介助者からの代理申請が可能です。登録解除の申請を希望される際は国保年金係までお問い合わせください。
※その他のマイナ保険証の詳しいご案内については厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用について 外部サイトへリンクします.
電子証明書の有効期限をご確認ください
電子証明書が有効期限を迎え3か月を経過すると、マイナ保険証が利用できませんので、早めの更新の手続きをお願いします。
保険料
「世帯」単位ではなく、「個人」で納付していただきます。
令和7年度の保険料は
均等割額+所得割額=1年間の保険料
均等割額:44,365円(全員が同額)
所得割額:{(1)前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)}×9.45%
【例】総所得金額が880,000円の方
44,365円+(880,000円-430,000円)×8.56%
=82,800円(100円未満切捨)・・・限度額は80万円
※均等割額については、軽減措置がありますので所得の申告を必ず行ってください。
※保険料は2年ごとに見直しされます。
保険料の軽減
【均等割額の軽減】
所得に応じて均等割額が軽減されます。
〇均等割の軽減
| 世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | ||||
| 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 | ||
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
7割軽減 | 44,365円 | 13,309円 | |
| 43万円+(30.5万円×被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
5割軽減 | 44,365円 | 22,182円 | |
| 43万円+(56万円×被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2割軽減 | 44,365円 | 35,492円 | |
【国保以外の保険の対象者で、被扶養者であったため今まで保険料を納めていなかった方の軽減】
| 均等割額 | 5割軽減 |
| 所得割額 | 0(当面の間、かかりません) |
※制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
※令和6年度・7年度の後期高齢者医療保険料についての詳しい説明はこちら(PDF)をご覧ください。
納付方法
保険料は、特別徴収(年金天引)か普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
ただし、年金の額が18万円未満の場合や介護保険料との合計が年金受給額の2分の1を超える場合などは特別徴収(年金天引)が適用されず、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
※国民健康保険を口座振替で納めていただいていた方の中には、後期高齢者医療保険も引き続き自動的に口座振替になると思われている方もいらっしゃいますが、後期高齢者医療保険は国民健康保険とは別の制度ですので、口座振替を希望される方は、新たに口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
対象者の住所変更
・県内での住所異動・・・制度運営は県単位ですから同一制度の中での異動となり、担当する市町村窓口が変更になります。
・県外への住所異動・・・異動先の県広域連合の被保険者となり、窓口は異動先の市町村となります。
★県外の特定施設入所のために住所変更する場合は、制度上、長野県後期高齢者医療広域連合の被保険者のままで窓口市町村も変わりません。これは、特定施設を有する市町村負担を軽減するための措置となります。施設入所による転出の際は国保年金係へご連絡ください。
自己負担(窓口負担金)
医療機関での窓口で支払う自己負担(窓口負担金)は、1割・2割又は3割となり、前年度の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
急激な負担増加に対する配慮措置の終了
窓口の負担割合が2割となる方について、自己負担額増額を最大3,000円とする配慮措置は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間適用されていましたが、令和7年10月からは、自己負担限度額が18,000円になります。
詳細につきましては長野県後期高齢者医療広域連合をご確認ください。
〇1か月の自己負担限度額(令和7年10月1日以降)
| 負担 割合 |
所得区分 | 自己負担限度額 | |
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 3割 | 課税標準額690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
|
課税標準額 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回 93,000円) |
||
|
課税標準額 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回 44,400円) |
||
| 2割 | 一般【2】 |
18,000円 |
57,600円 (多数回 44,400円) |
| 1割 | 一般【1】 | 18,000円 |
57,600円 |
|
区分【2】 |
8,000円 | 24,600円 | |
| 区分【1】 | 8,000円 | 15,000円 | |
※1 入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは支給の対象となりません。
※2 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
※3 (多数回)は診療を受けた月以前の12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担額です。
〇限度額適用・標準負担額減額認定証(1割の方)
令和7年8月1日より、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行が終了し、資格確認書へ負担区分の記載ができるようになりました。入院される場合等で負担区分の記載を希望される場合は、国保年金係に相談いただき、交付の申請をしてください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
〇限度額適用認定証(3割の方で所得課税標準額が690万円未満の方)
令和7年8月より、「限度額適用認定証」の発行が終了し、資格確認書へ負担区分の記載ができるようになりました。入院される場合等で負担区分の記載を希望される場合は、国保年金係にご相談いただき、交付の申請をしてください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は「限度額適用認定証」がなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
保険給付
次のような場合は、医療費を 一旦、全額お支払いしていただきますが、申請をいただき広域連合で認められれば、自己負担額を除いた額が後から療養費で支給されます。
- やむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合
- 保険診療を扱っていない医療機関にかかった場合
- 医師が必要と認めた、生血代、コルセット代、はり、きゅう、マッサージ等の施術代
- 医師が必要と認めた緊急移送費用
- 保険を扱っていない柔道整体師の施術を受けた場合
- 海外渡航中の受診
※保険給付の詳細につきましては長野県後期高齢者医療広域連合をご確認ください。
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111