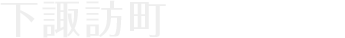児童扶養手当
最終更新日: 2025年4月1日
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
これまでに児童扶養手当の申請をされていない方で、申請をお考えの場合は(所得限度内になる方)、お気軽に教育こども課こども家庭相談係までお問い合わせください。
受給資格者
児童扶養手当を受けられる人は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者です。
※児童が一定以上の障がいを有する場合は、満20歳まで。
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
ただし、次の場合は手当が支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がない場合
- 里親に委託されたり、児童養護施設などに入所した場合
- 父または母の配偶者(婚姻の届出はなくとも事実上の婚姻関係にある場合を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしている場合
父、母または養育者が
- 日本国内に住所がない場合
- 公的年金給付(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができる場合 ※ただし、児童扶養手当よりも低額の公的年金を受ける方については、その差額分の手当を受けることができます。
手当の額
所得額及び児童の数に応じて、手当月額が異なります。
令和7年4月~
| 区分 | 月額 | 加算額 | |
| 第2子 | 第3子以降1人につき | ||
| 全部支給 |
46,690円 |
11,030円 |
第2子と同額 |
| 一部支給 |
所得に応じ |
所得に応じ 11,020円~5,520円 |
第2子と同額 |
※一部支給の支給額及び加算額は、下記の計算方法にしたがって算定されます。
- 第1子=46,680円-{(受給者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×0.0256619}
- 第2子以降加算額=11,020円-{(受給者の所得額-全部支給の場合の所得制限限度額)×0.0039568}
※{}内は10円未満四捨五入とします。
所得制限
手当を受ける方や同住所地に居住している扶養義務者(申請者の直系血族や兄弟姉妹)の所得が次の表の限度額以上ある場合、その年度は、手当の全部または一部が支給停止となります。
※養育費の受取がある場合、年間に受け取った額の8割相当額を所得に加算します。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
|
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注)上記限度額に加算できる場合
| 受給者本人 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 | |
| 70歳以上の同一生計配偶者1人につき | 100,000円 | |
| 老人扶養親族1人につき | 100,000円 | 60,000円 ※扶養親族が老人扶養のみの場合、2人目以降に加算 |
| 特定扶養親族1人につき | 150,000円 | |
| 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき | 150,000円 |
手当の支払い
県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の支給の対象になります。
年に6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)奇数月に前月までの各2か月分の手当が支給されます。
申請方法
- 申請に必要な書類を添えて、教育こども課こども家庭相談係にて手続きをしてください。
- 手当は申請月の翌月からの支給となります。手続きが遅れた場合、遡っての支給はできませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 申請者、対象児童、扶養義務者、配偶者(申請理由が障がいの場合)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 申請者の身分証明書(運転免許書、パスポート等)
- 申請者名義の口座がわかるもの
- 印鑑
※上記以外にも申請の内容よって必要となる書類があります。詳しくはお問合せください。
受給後に必要な手続きについて
現況届
毎年8月に、引き続き手当を受給する要件を満たしているかどうか審査し、11月分以降の支給額を決定するため、現況届の提出が必要になります。該当する方には事前に通知をお送りします。
現況届の提出がない場合、受給資格があっても11月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに手続きを行ってください。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 教育こども課 こども家庭相談係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111