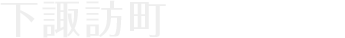保育園への入園
最終更新日: 2024年4月1日
保育園への入園について説明いたします。
保育園は、両親が働いていたり、他に保育できる人がおらず、家庭で乳児及び幼児を保育することができないときに、日中お預かりする施設です。保育園では、子どもたちが心身とも健やかに育つよう、日常の保育の他に、保育園の外での保育や、運動会・遠足などの行事も取り入れています。
子ども・子育て支援新制度に基づき、保護者が保育の必要な事由に該当し、2号(満3歳以上)・3号認定(満3歳未満)された児童をお預かりいたします。
認定期間は基準により異なり、入園後基準を満たさなくなった場合は通園できなくなります。
◆ 保育を必要とする事由
(★は通園できる期間を表します)
- 就労(会社員・パート・臨時・自営業・内職など)
★ 仕事をしている期間。仕事を失った場合は雇用保険の受給期間。 - 妊娠・出産
★ 出産予定月とその前後2か月を含む計5か月。(応相談)
その後も続けて通園するためには、2. 以外の基準を満たすことが必要。
- 保護者の疾病・障害
★ 療養等に必要だと医師が認めた期間(要診断書) - 同居親族の介護・看護
★ 介護・看護に必要だと医師が認めた期間(要診断書) - 災害復旧(震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている)
★ 復旧に必要な期間 - 求職活動
★ 求職活動に係る証明書の提出後、仕事を始めるまで(最長3か月) - 就学
★ 就学中の場合は在学期間(要証明書)
注: 趣味の講座やカルチャースクールなどを除く - 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
★ 育児休業取得期間(要証明書)
注: 3歳以上児かつ保育園の定員に空きがある場合に限る。
◆ 保育時間
午前7時30分~午後6時30分
注: 保育の必要量に応じて、「保育標準時間」または「保育短時間」の保育となります。
【保育標準時間】 午前7時30分~午後6時30分
【保育短時間】 午前8時00分~午後4時00分
■ 保育の必要量
a. 保育標準時間 → フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) 労働時間120時間以上/月
b. 保育短時間 → パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間) 労働時間120時間未満/月
◆ 手続き
- 10月初旬に入園説明会を開催し、入園案内、申込書、受付日程表等をお渡しします。
10月下旬に各保育園で申込受付と入園園児の面談を行います。
◆ 保育料
- 保育料は、世帯の町民税所得割額から階層区分判定されます。
- 年度途中に保育料の切替があります。
令和6年4月~令和6年8月 → 令和5年度の町民税所得割額により算出
令和6年9月~令和7年3月 → 令和6年度の町民税所得割額により算出
|
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
月額(円) |
||||
|
階層 |
定義 |
3歳以上児 |
3歳未満児 |
||
|
保育短時間 保育標準時間 (円/月) |
副食費 (おかず代) (円/月) |
保育短時間
(円/月) |
保育標準時間
(円/月) |
||
| 第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及びに永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 第2 |
市町村民税非課税世帯かつ母子世帯等 |
0 |
0 |
||
|
市町村民税非課税世帯 |
0 |
0 |
|||
| 第3 | 市町村民税所得割課税額が48,600円未満かつ母子世帯等 |
9,000 |
9,000 |
||
| 市町村民税所得割課税額が48,600円未満である世帯 |
17,500 |
18,500 |
|||
| 第4 |
市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満かつ母子世帯等 |
9,000 |
9,000 |
||
| 市町村民税所得割課税額が48,600円以上97,000円未満である世帯 | 0 |
4,500 |
27,500 | 29,500 | |
| 第5 |
市町村民税所得割課税額が97,000円以上169,000円未満である世帯 |
41,000 |
43,500 |
||
| 第6 |
市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満である世帯 |
57,500 |
60,000 |
||
| 第7 | 市町村民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満である世帯 |
64,000 |
67,500 |
||
| 第8 |
市町村民税所得割課税額が397,000円以上である世帯 |
66,000 |
69,500 |
||
◆利用者負担(保育料)の軽減について
(1)兄弟同時入所
- 2人同時入所の場合、入所している2人目が半額になります。
- 3人以上同時入所の場合は、入所している2人目が半額、入所している3人目以降が無料になります。
(2)低所得世帯や多子世帯等の特例軽減
- 第1~第4階層で、国の定める基準を満たす家庭は、同時入所でない場合にも、軽減または無料になるため、税情報や現況届等に基づき判定します。
(3)多子世帯の軽減
- 児童を3人以上養育している家庭は、同時入所でない場合にも、第3子以降の児童の保育料について、3歳以上児は無料、3歳未満児は本来負担する額の半額になります。
※軽減について、(1)と(3)は併用できますが、(1)と(2)は併用できません。
◆副食費(おかず代)について
- 2号認定(3歳以上児)のみ実費徴収となります。
- 第4階層の一部(年収360万円以上相当世帯)~第8階層に該当する、第1~2子目が実費徴収の対象となります。
- 第1~第4階層の一部(年収360万円未満相当世帯)に該当する全ての児童、及び全階層の同一世帯内第3子目以降の児童は実費徴収が免除になります。
◆ 母子世帯等とは次の(1)及び(2)に該当する世帯です。
(1)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯。
(2)養育している児童または父母のなかで、在宅障害児(者)のいる世帯。

このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 教育こども課 保育係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111